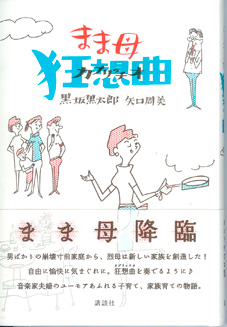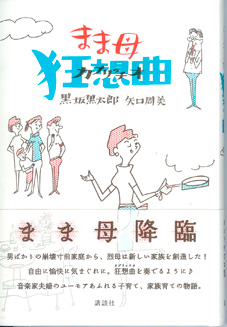
まま母降臨
男ばかりの崩壊寸前家庭から、烈母は新しい家庭を創造した!
自由に愉快に気まぐれに。
狂想曲(カプリッチオ)を奏でるように
音楽家夫婦のユーモアあふれる
子育て、家族育ての物語。
講談社 6月24日発売
1、575円
長男は妻が倒れてすぐに留学先のアメリカから帰国した。妻が入院中僕とかわるがわる看病をしてくれ、葬式の後もアメリカへ帰らず、来年の春、日本の大学を受験しなおすのだと、予備校に通っていた。彼の志望する大学は京都にあった。
「そんなこと分かっているよ。おまえは京都にいけばいい。おれと悠樹で大丈夫だ。お手伝いの山田さんもいるし・・・」
うつむき加減に言う僕に長男は
「あんなおばさん、まだ当てにしてんの?あんなことされておきながら」
とさらに語気を強める。
「あんなことって?」ときく佳美ちゃんに、長男は説明し始めた。
実は、その数日前、僕ら家族にとってショックな事件が起きていた。
僕ら家族は妻が逝ってしまってからしばらくは、男三人家事を分担しながら、頑張っていた。ただ、長男は受験生、僕は妻が入院しているあいだまったく手につかなかった仕事がたまり、その処理に追われていた。次男の悠樹は中学校生活が一番のっているとき、部活などでおお忙し、使ったままの食器はたまる、洗濯物はたまる、掃除もできず家のすべてのものがクスミ、廃屋のようになっていく。そんな状況に耐えられず、僕は役所に「父子家庭を支援してくれる制度がないか」と、相談に出向いた。
「そんなものはありません」と役所の態度は実に冷たい。
「母子家庭はいろいろあるって聞いたんですけど」と食い下がる僕に
「母子家庭のための制度がありますよ。でも父子家庭はねえ」
「本当に困っているのです」と実情を話すと、
「父子家庭のためというわけじゃないけど、こんな家庭支援グループがあるので連絡とってみたらどうですか?」と手作りのパンフレットをくれた。それは、婦人達が何人かで寝たきり老人や障害者の皆さんの家庭を支援するために活動しているグループで、形は家政婦さんなのだが、料金は家政婦協会の派遣などに比べたら格安で家事一般をしてくれると言うことだった。婦人達にとっても、普段家で夫や子どもにしてやっている事をするだけでこずかい稼ぎができるのだから、こんなにいいバイトはないのかもしれない。
すがるような気持ちで、手作りパンフレットに書かれたグループの代表者の電話番号に連絡をすると、
「奧さんを亡くされたのですか、お気の毒ですねえ、男性ばかりでは大変でしょう。すぐに適当な方を送りましょう」と60すぎの元気なおばさんを派遣してくれた。このおばさん、それから、週3回ほど我が家に来てくれ、手際良く掃除、洗濯をし、また料理も野菜を中心にしたお袋の味を提供してくれ、僕も子ども達もとても助かった。ところが、最初はよかったのだが、慣れてくるに従い、こちらを「男ばかり」とみくびったような仕事が見えてきた。そして事件は起きた。
ある夜、僕は遅い時間に帰宅した。帰ると子ども達はふたりとも起きていて、
「おばちゃんがおでん作ってくれて、俺達もう食べた。親父の分、残してあるから食べな」
とやさしいことを言う。はらがへっていたのでさっそくいただきにかかった。おいしそうなおでんである。一口食べた。確かにマズクはないのだが、味が何か少し妙だ。まあこれもおばさん特有の味の付け方なんだろう、そうおもいながら食べていった。半ペン、こんにゃく、こんぶ。おでんの定番が入っている。おばさん、子ども達のために色々材料買ってくれたんだ、と感謝いっぱいで食べて行った時だ、どうも舌ざわりがジャリジャリする、なにかアサリでも入れてくれたのだろうか?そう思いながら土鍋の底をのぞきこむと、黒い小さな粒が無数に沈んでいる。
「なんだろうこれ?砂にしてはツブが大きいな」と
首をかしげたときだ、僕の目に破れた小さな紙の袋が飛びこんだ。その瞬間、僕は
「ウオーッ!」と叫んだ。叫び声に驚いてふたりの息子が食卓に飛んできた。
「どうした?親父?」
やってきた二人に僕は鍋の底の破れた袋を取りだして見せた。
「保存剤じゃねえか、これ。「食べられません」て書いてあるぞ」長男が叫ぶ。
「やべえ、いっぱい食っちまった」次男はそう言いながら、流しに行き水道の蛇口をひねりウガイを始める。
「バカ、もう遅いよ。そんなことしたって。まったく、俺達を殺す気かよ」
長男は怒り狂っている。
僕は怒る気にもならなかった。そして怒るかわりに泣けてきた。
保存剤なんかで死にはしない。死にはしないけど・・。
おばさんはスーパーで「おでんセット」を買ってきて、それをそのままボンと鍋に入れたのだろう。一緒に入っている保存剤も見えなかったぐらいだから、本当にボンと、「どうでもいいや」とばかりに入れたのだろう。おばさん、自分の息子にだったらそんなことするだろうか?おそらく「おでんセット」を買ってきたとしてもひとつひとつ丁寧に具を入れ、心を込めて料理するだろう。保存剤と一緒におでんを煮込む、というようなことは絶対にしないだろう。僕はおばさんに特別なことをして欲しい、と言っている訳ではない。おばさんが普段家でしていることと同じ事でいいから僕らの家庭にもして欲しかった。おばさんの作る料理がまったく愛情のこもっていない、事務的な料理でしかないことを破れた保存剤の袋が語っていた。その袋がまるで今の僕らの家庭のようで、情けなく、惨めで涙がとまらなくなった。
翌日、グループに厳重に抗議し、責任者は「大変申し訳ない」と謝ってくれたのだが、こちらが提案した派遣員交代の話は「他に適任者がいないのでもうしわけないけど・・」ということで却下された。引き続きそのおばさんが我が家を担当することになった。おばさんは数日後やってきて、「責任者から電話もらいましたが、すみませんでしたねえ。でもあれは害はないって言うから」と開き直っている。僕は憮然としていた。
その事件の話を聞いた佳美ちゃんは、「そりゃひどすぎー」と可愛い口をとがらせている。
そして「おじさんやっぱりお嫁さんもらいなよ」という。
長男はその言葉を誘い水としてまた僕に言う
「あのね、親父はね、今、独身なんだよ。わかる?独身って言うことは、誰と結婚してもいいっていうことなんだ。人生の幅がすごく広がったということなんだ」
「そうそう」佳美ちゃんが頷く。
「場合によっちゃ俺の高校の時のクラスメイトとだって結婚できるんだよ」
「バカなこと言うなよ、そりゃ犯罪だよ」
「そんなことないよ。20も30も年の離れた夫婦は世の中にいっぱいいるってテレビでやってたよ。佳美と結婚したっていいんだよ。なあ佳美」
「そうそう、私、おじさんのお嫁さんになっちゃおうかな」可愛い舌をペロと出しながら佳美ちゃんが言う。
「ふざけたこと言ってないで早く食べろ!」
いきり立つ僕を後目に息子は佳美ちゃんに言う
「おまえが俺の親父と結婚したら、おまえはおれの母親か。「佳美かあさん」か、いいな、なかなか」僕はそば食べるのをやめ叫んだ。
「いいかげんにしろ!」
子ども達にさんざんコケにされ僕は怒り狂ったが、怒りながら「確かにナントカしなければ」と考え始めていた。
「言っとくけどね。俺は来年の春にはこの家を出ていかなきゃならないんだからね。そうなりゃ親父と悠樹ふたりだよ。暮らしていける?」